Location
語源の話 (楽器編)

clavicembalo italian
clavecín /clavicémbalo spanish
cravo Portuguese (語源不明)
clavecin French
harpsichord
clavicembaloの語源を調べてみると、ラテン語のclāvicymbalum(clavis+cymbal)から、となっています。
cymbalumはwikitionaryにおいてはラテン語のところで、語源や名詞の性・格変化のタイプの説明と共に次の様に2つの意味が載っています。
1 cymbal
2 (poetic,syncopated ) genitive plural(複数属格) of cymbalum
つまり、
1 シンバル
2 (詩歌において)cymbalumの複数属格形cymbalōrumの語中母音消失形
注 語中音消失(cyncopate)とはアクセントの無い音節が省略される事。 (cf. 音楽でいうシンコペーション)
従って、clavicembaloは、この第2の意味のcymbalum(ダルシマー類)に鍵盤を付けたものの様です。
従って、本当はチェンバロという言い方は不完全です。 clavicembaloクラヴィチェンバロと言ってはじめて鍵盤の付いた楽器となります。
なお、gravicembaloについては別途記載予定です。

clavicordo italian
clavicordio spanish, old italian
clavicórdio Portuguese
clavicorde French
clavichord
備考;cravoは現代ポルトガル語ではharpsichordを意味する。
clavichordium←clavis(key)+chorda(cord)
語源的にはこの通りラテン語の「キー」と「弦」の合成語である。 しかし、これが何を意味していたかは別問題である。 つまり、古くはこれが一般にチェンバロを指していることが多い。 クラヴィコードはmonocordio等と呼ばれている事が多い様だ。 つまり、クラヴィコードはモノコードが一弦でなく複数の弦を持ち、左右の手で同時に奏でることができるようになっても、まだモノコードと呼ばれていたそうだ。(以前、マニャーノのクラヴィコードシンポジウムへ行った時、話題になっていた。) The Clavichord (Bernard Brauchli Cambridge University Press, 1998)に詳しい説明がある。 古い文献を読まれるときは、まずこれに目を通されると良い。

oboe italian
oboe spanish
oboé Portuguese
hautbois French
oboe
オーボエの語源はhautboisであり、フランス語である。 フランスにてショームより改良され誕生したものだ、と言われている。 boisは木という意味だが、楽器においては木管楽器を意味する。 hautは基本的には(ピッチが)高いという意味だ。 このhautは現代フランス語でも、副詞の場合は音が高い、と同時に声が大きいという意味で用いられる。
従って、音が大きな木管楽器なのかもしれない。
余談だが、オーボエがオーケストラに入った最初の木管楽器だと言われているが、それはフランスにおいて Jean-Baptiste Lullyが宮廷音楽監督だった時に「王の24のヴィオロン」という弦楽オーケストラにオーボエを含むダブルリードバンドを加えた事を指していると思われる。
リュリはグラン・モテ等大きな編成の時は、Les Vingt-quatre Violons du Roy つまり24のヴィオロン(ヴァイオリン族による弦楽オーケストラ)にLa Grande Écurie du Royを加えたそうだ。 この様に常設オーケストラに管楽器が加わったのはリュリの時代、つまり17世紀後半である。 なお、1664年にショームから改良された新しい楽器(今日でいうところのバロックオーボエ)が現れたことにより、この楽器によるダブルリード楽器によるバンドのためにマルシュを書いているそうである。

orchestra italian
orquesta spanish
orquestra Portuguese
orchestre French
orchestra
イタリア語の辞書でorchestraを引くと次の3つの意味が載っている。
1オーケストラ
2オーケストラボックス/オーケストラピット
3古代ギリシャ、ローマの円形劇場における舞台前の半円形ないし円形に近い土間の部分
(ここでコーラスや踊りが行われた。)
この3番目の意味がもともとの意味である。
英語ではイタリア語と同じスペルであるが、これはラテン語から直接取り入れたのかもしれない。
orchestraは古い言葉を元にしているようだ。 Wiktionaryにおいてorchestraのethymology(語源学)について次の様に説明されている。
From Latin < Ancient Greek ὀρχήστρα (orkhḗstra) < ὀρχοῦμαι (orkhoûmai, “to dance”) (an intensification of ἔρχομαι (érkhomai, “to go, come”), from Proto-Indo-European *ergh- (“to set in motion, stir up, raise”)) + suffix *-tra denoting "place".
ラテン語のorchestra←古代ギリシャ語ὀρχήστρα (orkhḗstra)←ὀρχοῦμαι (orkhoûmai, “踊る”) 、これは ἔρχομαι (érkhomai, “行く、来る”のan intensificationとして作られたものだが。 orchestraはインド・ヨーロッパ祖語の*ergh- (“起こす、起動する”)) + suffix *-tra denoting "place".場所を意味する接尾辞-traで出来ている。 一言で言えばorchestraは踊る場所という意味である。
pianoforte italian
piano spanish
piano Portuguese
piano French
piano
イタリアのチェンバロ製作家のBartolomeo Cristofori (1655-1731)が1700年ごろハンマーで弦を叩く楽器を作り、これを gravicembalo col piano e forte すなわち「ピアノとフォルテがでるグラヴィチェンバロ」と名付けた。 これが今日でいうピアノの誕生と考えられている。 なお、col は英語のwith theに相当する。 ここでいうgravicembaloのgraviはgraveの意味であろう。 音楽用語でgraveは「荘重に」となっているが、graveはもともと重大な、重いといういみである。 これらの意味に続いて「音の低い」と言う意味がある。 辞書によればcon voce graveで「低い声で」という意味だそうだ。 従って、gravicembaloは「低音チェンバロ」と言う意味となる。 どれくらい低音であるかは決まっていないのかもしれない。 クリストフォリの活躍した時代、C/Eのショートオクターブのチェンバロ、すなわちclavicembaloに対して、Cよりクロマティックにある楽器をgravicembaloと呼んだのかもしれない。 さて、このgravicembalo col piano e forteは略されてpianoforteとなった。 ピアノの略号がpfなのはこのためである。 これをさらに略してpianoと読んでいる国もある。 ただし、イタリア語ではpianoは名詞では面、平面、建物の階、レベル等を意味し、形容詞では平らな、平易な、やさしい、というように多くの意味を持った日常語であり、pianoだけでは意味が分からない。 従って、今でもpianoforteと呼ばれる。 また、英語等でもpianoforteと言われる事がある。

viola da gamba italian
viola de gamba spanish
viola de gamba Portuguese
viole French (ヴィオール)
viol (ヴァイオル)
viola da gambaは足のヴィオラと言う意味だ。 このviolaはviolinoの項で述べた通り、弦楽器と言う意味である。 古プロヴァンス語において、violeという語が用いられ、現代フランス語でもそのまま用いられる。 中世において代表的な弓奏弦楽器にvielleがあるが、これもフランス語である。 このvielleからフランス語のviole、英語のviolあるいはスペイン語のvihuelaが派生したのかもしれない。 いづれにしても、中世に遡って考察するにはvielleを中心に考えた方がよさそうである。
なお、現代フランス語におけるvielleは基本的には弓奏弦楽器を意味するが、現代の楽器としてはvielle à roue(ハーディーガ―ディー)を意味する事が多い。
語源の話からそれるが、弓奏弦楽器は次の様な由来を持つようである。
Rebab(アラビア)→ Byzantine lyra/ lira(旧東ローマ帝国)→ vielle(西ヨーロッパ)
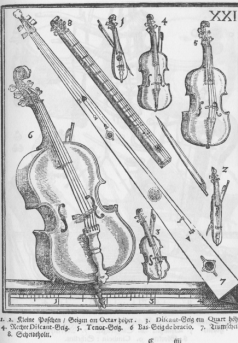
violino italian
violín spanish
violino Portuguese
violon French
violin
violino←viola+ino(縮小辞)= ヴィオラの小さいもの ....italian
さて、このviolaの語源をたどるとだいたい次の通りである。
viola←old Provançal古プロヴァンス語←vitula (中世ラテン語)
なお、Wiktionaryによればこのvitulaは語源上はRoman goddess of joy and victoryであり、また、次の様に説明されている。
1.a stringed musical instrument 弦楽器一般
2.calf, young cow
古プロヴァンス語は南フランスで話されていたオック語の一種である。 また、西ローマ帝国崩壊後、ラテン語以外では最初期に文章に用いられた言語だそうである。 また、 オック語は11世紀末から 13世紀末にかけて活躍した 南フランスの吟遊詩人トルバドゥールtroubadoursが用いた言葉でもあった。 なお、現在のフランス語はフランスの北部で話されていたゲルマン語基を含むオイル語がベースとなっているため、ラテン語の他の子孫、スペイン語やイタリア語等と少し異なる部分がある事にお気づきの方もおられると思う。

violoncello italian
violonchelo spanish
violonceloPortuguese
violoncelle French
cello
violoncello=viola+one(拡大語尾)+ cello(縮小語尾)....italian
一言で言えば、ヴィオラの大きくしたものをちょっと小さくしたもの。
チェロは縮小語尾だからチェロだけでは何も意味しない。 略す時もvcと書かれるのはそのためだ。
なお、cello の女性形cellaは名詞としては小部屋を意味する。 camera(部屋)が女性名詞だからであろう。 また、関連する語としてはcellura(細胞)などがある。
また、英語のwine cellarのcellarはこの小部屋の意味である。
なお、このvioloncelloに、さらに小さいという形容詞piccoloを付けてvioloncello piccolo という楽器もある。 この楽器をチェロピッコロを呼ぶ人がいるが、これでは縮小辞に縮小語を付けた形になってしまい、踏んだり蹴ったりで楽器がかわいそうである。 英語でもイタリア語と同じくvioloncello piccoloと正しく呼ばれる。